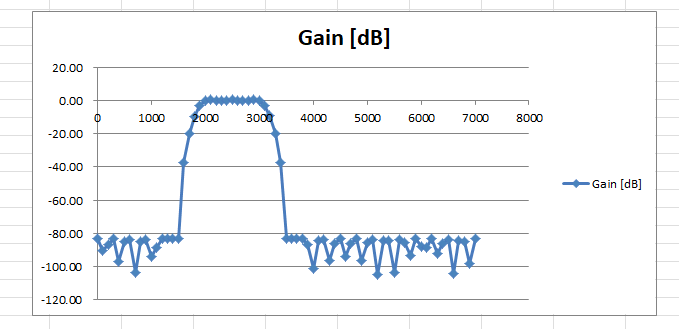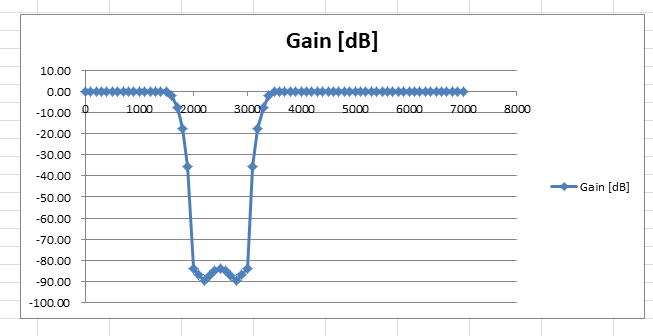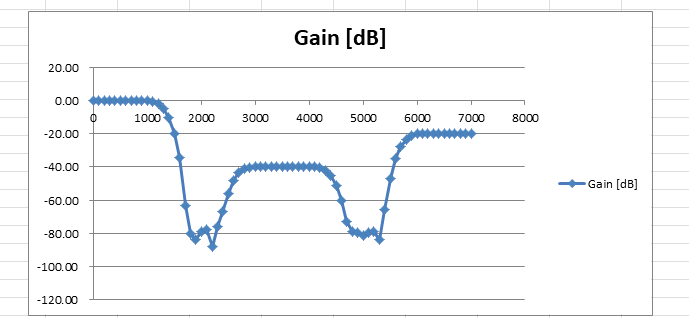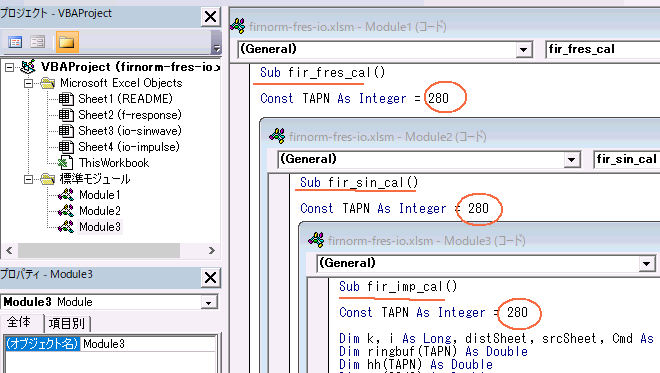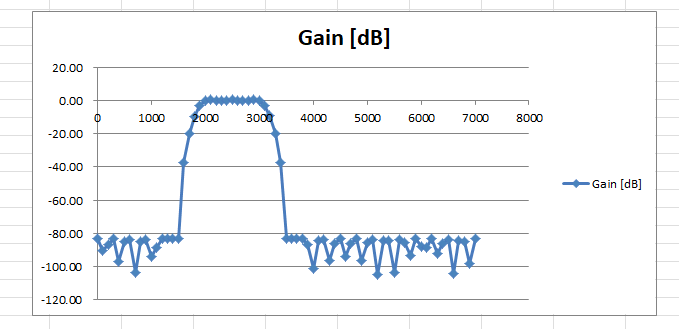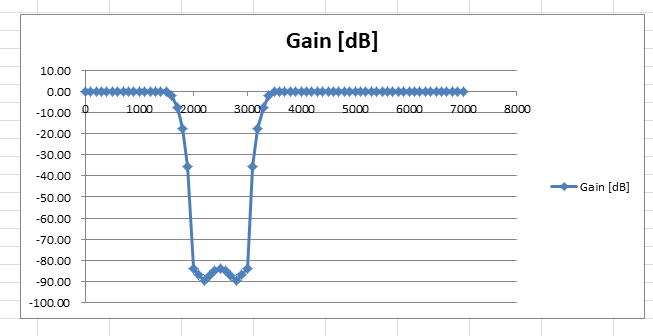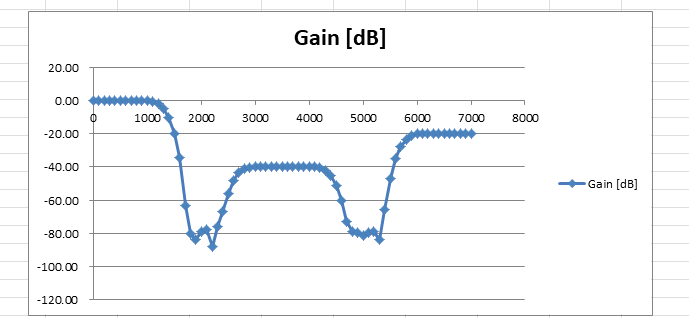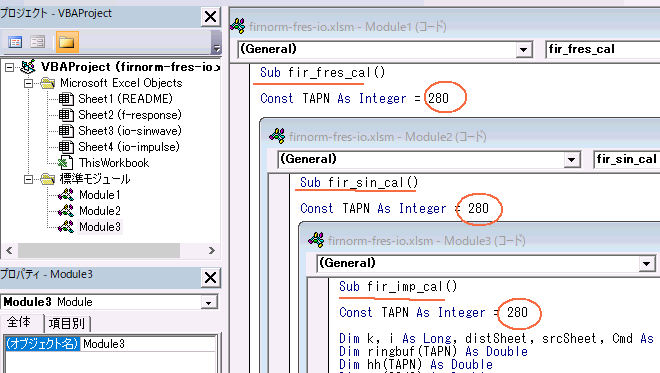3-03 タップ数を増やしてより急峻・複雑な特性(続き)
●特定の帯域を通過させるフィルタ
次はBPF(Band Pass Filter, 帯域通過型フィルタ)です。これから係数をコピーしてf-responseシートのD列にペーストしてみましょう。周波数特性は図3‐36のようになります。1500〜2000Hzで急峻に上がり、3000〜3500Hzで急峻に下がります。 |
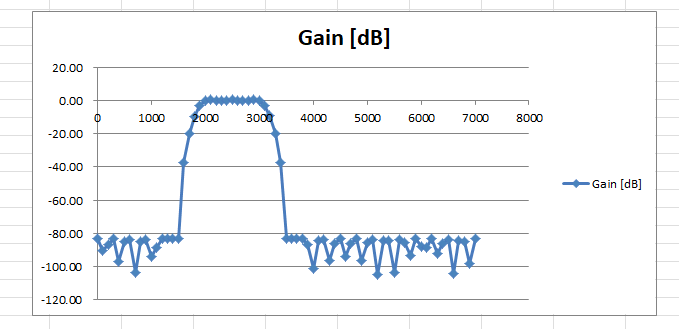
図3-36 2kHz〜3kHzを通すBPF
●特定の帯域を減衰させるフィルタ
さらにBRF(Band Reject Filter, 帯域除去型フィルタ)です。これから係数をコピーしてf-responseシートのD列にペーストしてみましょう。周波数特性は図3‐37のようになります。1500〜2000Hzで急峻に下がり、3000〜3500Hzで急峻に上がります。 |
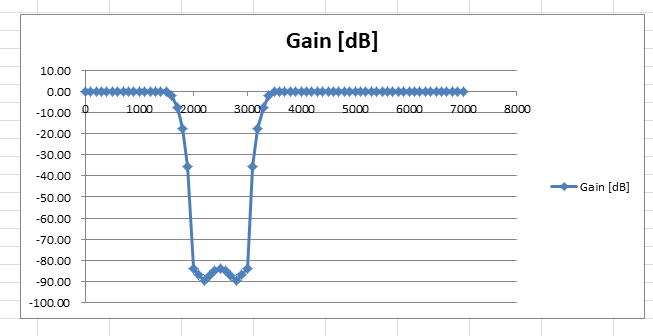
図3-37 2kHz〜3kHzを通さないBRF
●帯域を上げたり下げたりするイコライザ
FIRフィルタでタップ数が280にもなると様々な特性を持たせることができます。図3‐38のようなイコライジングも可能になります(この係数をコピペ)。 |
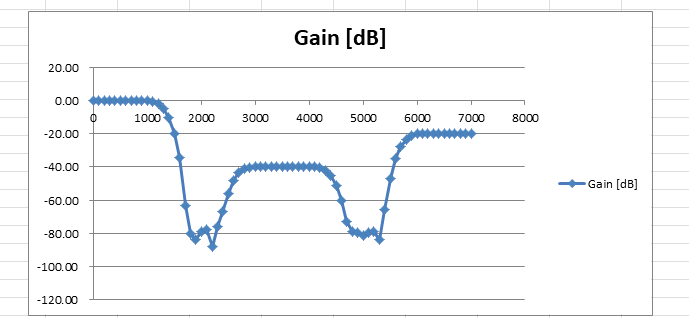
図3-38 低域は0dB, 中域は-40dB, 高域は-20dB, 境界域は-80dB
●タップ数が一定なら特性によらず遅延量が一定
FIRフィルタの遅延量はタップ数で決まり、280タップなら(280-1)/2/44.1kHz = 3.16msとなります。この値はLPF/HPF/BPF/BRFでもイコライザでも同じです。
図3‐39は上記イコライザのインパルス応答ですが(VBAのModule3をTAPN=280として実行)、これを見ると3.16ms遅延するのを納得できるのではと思います。 |

図3-39 インパルス応答の真ん中が遅延量になる
●VBAを使う際の注意点
タップ数(デフォルトで140)を変更する場合は、図3‐40のようにVBAの各モジュールのTAPNの値を変更しましょう(これを忘れると周波数特性や出力の計算がおかしくなる)
|
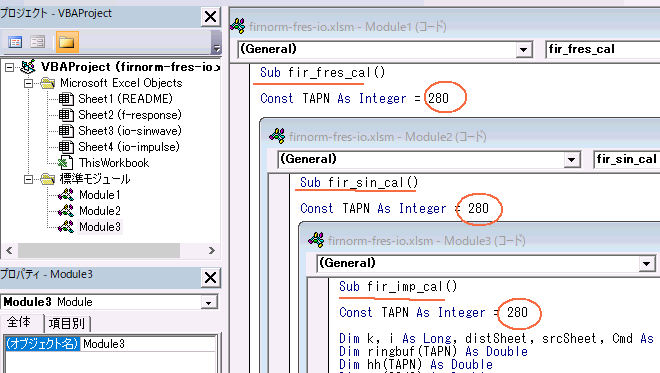
図3-40 Module1〜3、それぞれTAPNを変える
●パラメータを変えたらVBAを実行する
タップ数が同じでも何かパラメータ(係数、入力サイン波の周波数など)を変更したらVBAを実行してください。計算は基本的にVBAで行います。 |
最初のページへ
目次へ戻る |