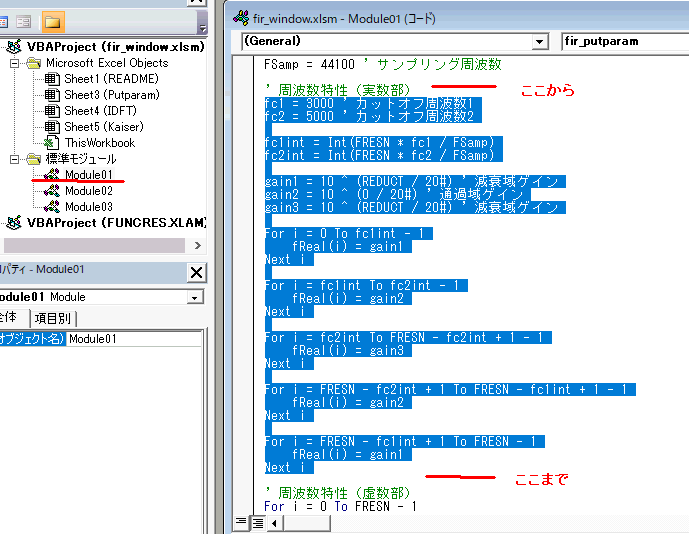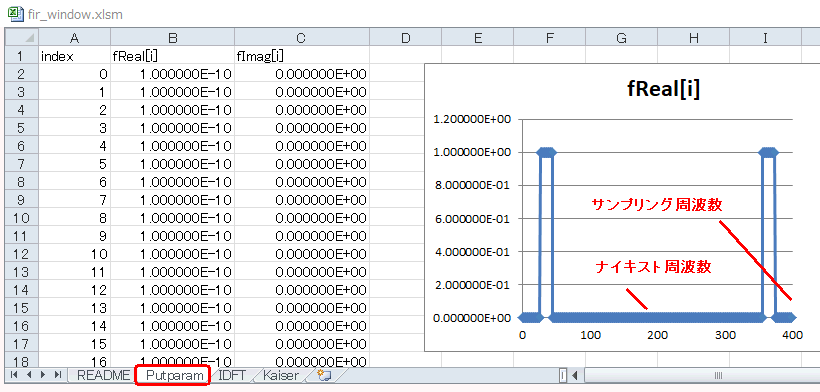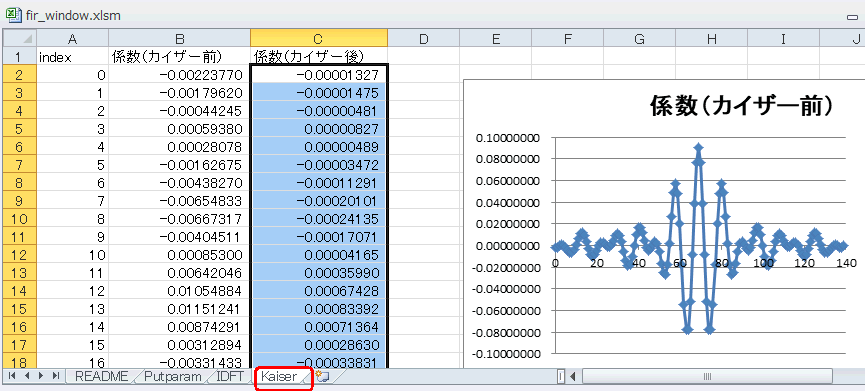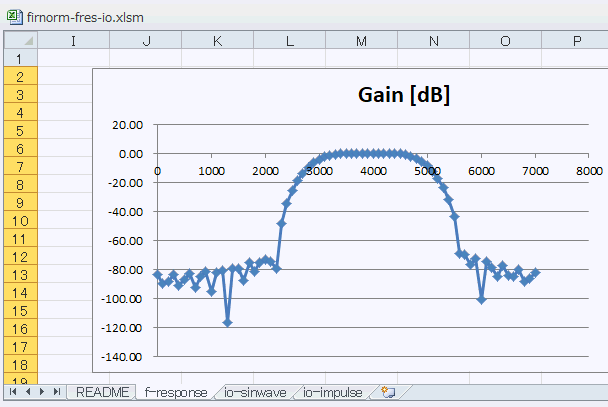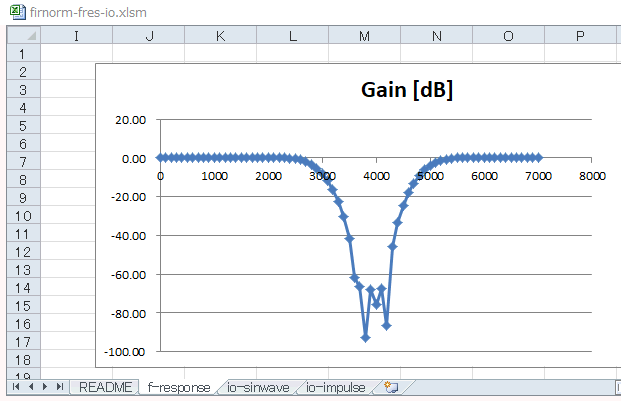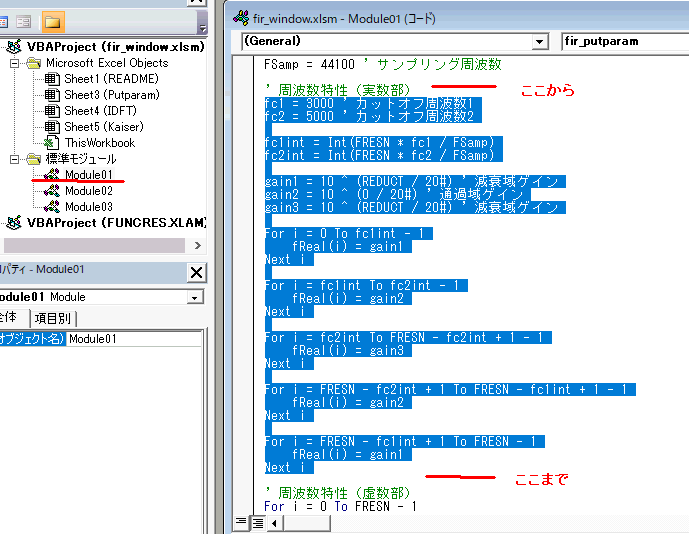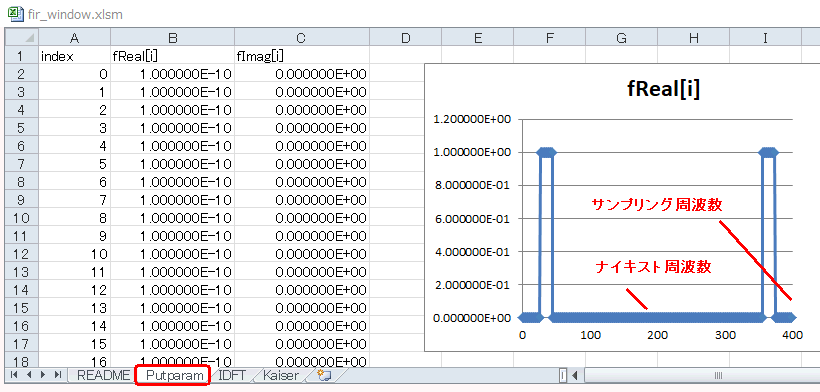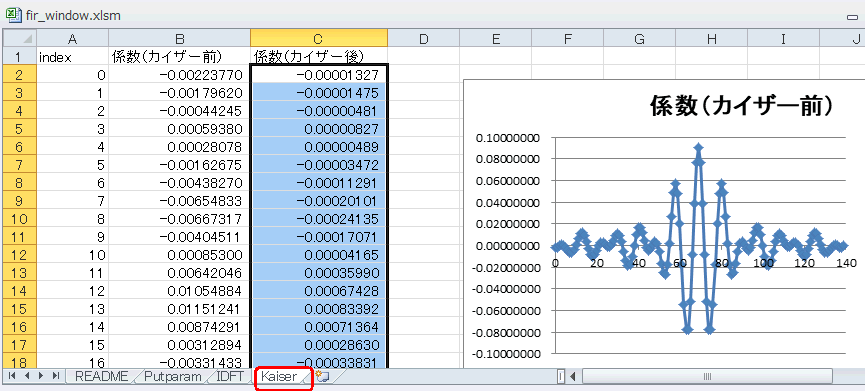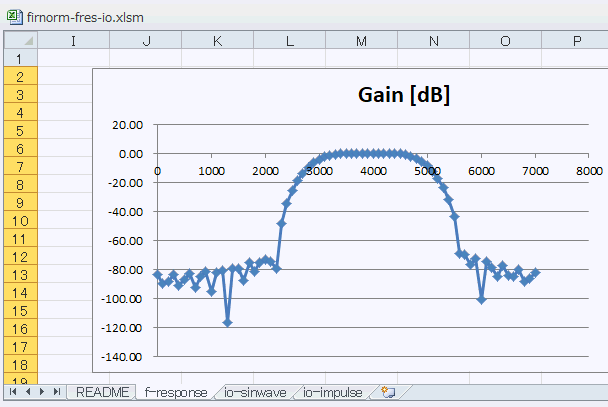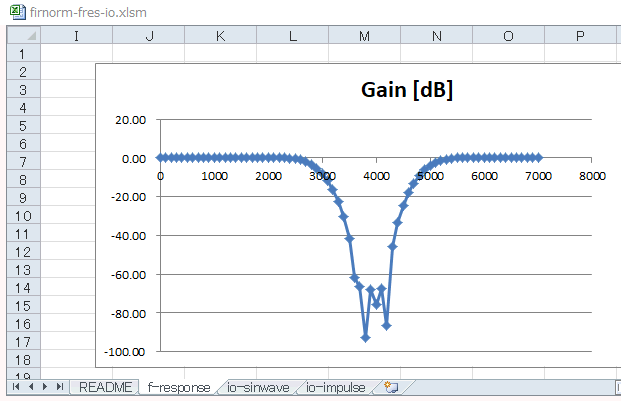7-02 HPF/BPF/BRFの係数を窓関数法で求める(続き)
●帯域通過フィルタ
今度はBPFの係数を求めます。これをコピーしてModule01の「周波数特性(実数部)」の部分に上書きします(図7‐27)。 |
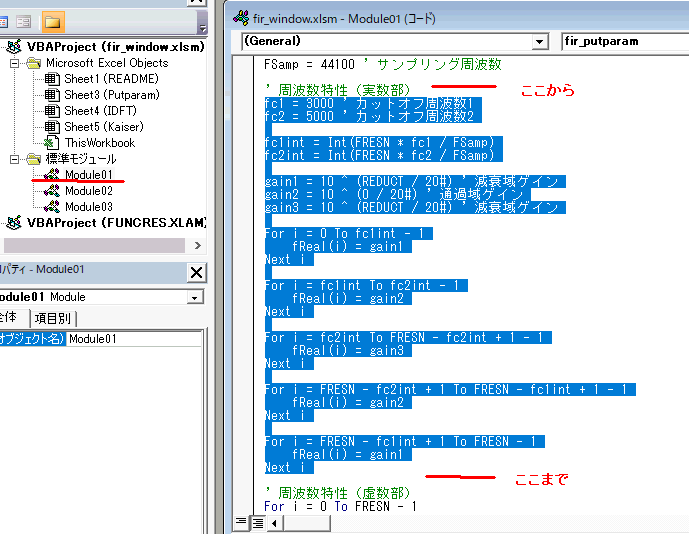
図7-27 Module01のこの部分を入れ替え
●変更はModule01だけ。Module02, 03はそのまま実行
Module01を実行すると図7‐28のように帯域通過特性になっています(ナイキスト周波数までを見る)。 |
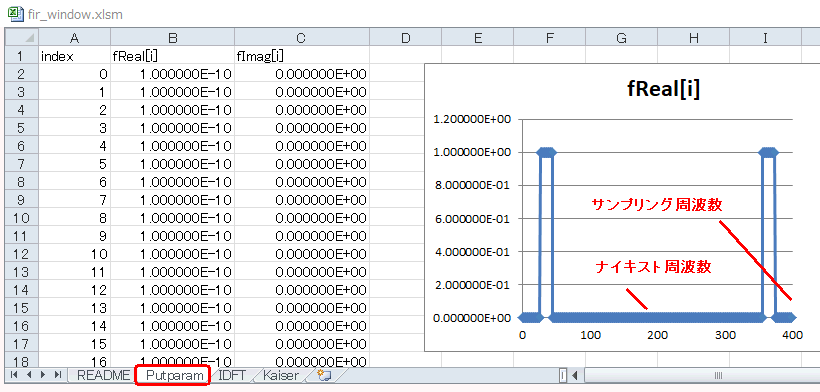
図7-28 帯域通過特性を与える
| その後、Module02, Module03と実行すると、BPFの係数が得られます(図7‐29)。C列(カイザー後)の係数をコピペし、別EXCEL(firnorm-fres-io.xlsm)でF特を計算させます。 |
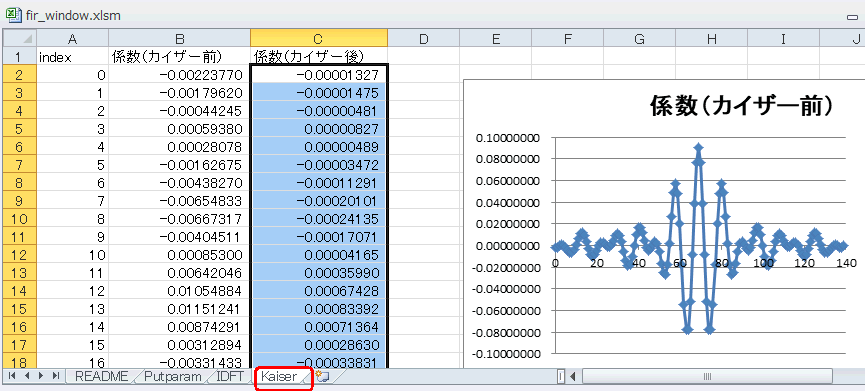
図7-29 カイザー後の係数をコピー
| 別EXCELで計算させてみると、図7‐30のように3000〜5000Hzを通すBPFになっています。 |
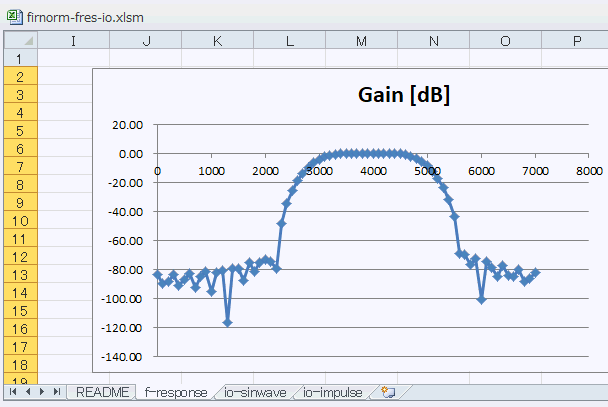
図7-30 中域だけを通すフィルタ
●帯域除去フィルタ
BRFを設計するにはModule01を図7‐31のように変更します(減衰域と通過域を逆にする)。Module02, 03はそのまま実行します。 |

図7‐31 変えるのはこの部分だけ
| 得られた係数を別EXCELにコピペし、F特を計算させると、図7‐32のように3000〜5000Hzを遮断するBRFになります。 |
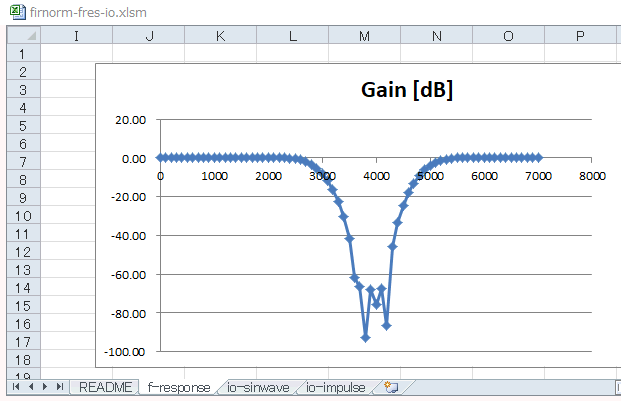
図7‐32 低域、高域を通すフィルタ
●パラメータをいろいろ変えてみよう!
窓関数法によるFIRフィルタ係数の導出は次のようになります。
①周波数特性の決定
②逆DFTでインパルス応答を得る
③窓関数の乗算
LPF/HPF/BPR/BRFとフィルタタイプを変更するには、①のステップを変更するだけです。またカットオフ周波数、サンプリング周波数の変更も①で行います。
またタップ数(係数の数)の変更は③のステップで行います。Module03のTapN=140から変更しますが、逆DFTの点数が400であることにより最大タップ数は400となるのに注意しましょう。
|
最初のページへ
目次へ戻る |